区画整理とは?制度の基礎知識や注意点を徹底解説
「突然、行政から区画整理のお知らせが届いた」「家の前の道路が広くなるらしいけど、うちはどうなるの?」
このように区画整理という言葉を初めて目にして、不安や疑問を抱く方は少なくありません。
区画整理は、街の道路や土地の形を整えて暮らしやすくするために行われる制度ですが、その仕組みや影響は一見すると分かりづらいものです。
土地の一部を提供しなければならなかったり、場合によっては家を建て替える必要が出てきたりと、大きな変化が伴うこともあります。
この記事では、「区画整理とはそもそも何か?」という基本から、「自分の土地や家にどんな影響があるのか?」「費用負担はあるのか?」といった疑問まで、丁寧に解説します。
今後の暮らしや土地活用に備えて、ぜひ参考にしてください。
目次
- 区画整理とは?意味と目的をわかりやすく解説
- 区画整理の仕組みと流れ|土地はどう変わる?
- 知っておきたい!区画整理で使われる主要な用語
- 区画整理のメリット・デメリットを徹底比較
- 区画整理にかかる費用と補償制度:自己負担はどれくらい?
- 区画整理と自宅・土地の関係:建て替え・売却・相続への影響
- 区画整理が「まだ関係ない人」にも重要な理由
- 区画整理の進み方と期間
- まとめ
1.区画整理とは?意味と目的をわかりやすく解説
区画整理の定義:街を生まれ変わらせる一大プロジェクト
区画整理とは、正式には「土地区画整理事業」と呼ばれ、老朽化したインフラや無秩序に並ぶ住宅地などを整え、街全体の利便性や安全性を高めるための都市計画制度のひとつです。
区画とはどういう意味?
→土地などをいくつかの部分に区切ること。また、その区切った一つ一つ。
引用:コトバンク 区画

具体的には、以下のような整備が行われます。
- 狭くて通りづらかった道路の拡幅
- 公園や広場の新設
- 地形がいびつだった土地の区画の整理
- 下水道や歩道など生活インフラの整備
このような整備を通じて、災害に強く、暮らしやすい街づくりが実現されます。
土地の所有者にとっては、「土地の形や面積が変わる」「仮移転が必要になる」といった影響がありますが、長い目で見ると街全体の資産価値や暮らしやすさの向上につながる点が特徴です。
誰が行うの?事業の主体と種類
区画整理とは、老朽化した街並みや道路、土地の形状などを整備し、より快適で住みやすいまちをつくるための大規模な都市整備事業です。この区画整理事業を実際に行うのは、主に以下のような主体に分かれます。
公共団体施行(行政主導型)
もっとも多いのが、市区町村などの地方自治体が主体となって行う「公共団体施行」です。計画立案から資金調達、工事の実施まで行政が責任を持って進めるため、比較的スムーズに事業が進行しやすい特徴があります。都市再生や防災対策など、公共性の高い目的で実施されることが多く、税金が活用されます。
組合施行(土地所有者の共同事業)
土地の所有者が集まって「土地区画整理組合」を設立し、自ら事業を進める「組合施行」もあります。行政のサポートを受けながらも、土地所有者の合意形成が必要であり、時間がかかるケースもありますが、自分たちのまちを自分たちで再生できるというメリットもあります。
個人施行や独立行政法人施行など
まれに、特定の個人や民間企業、UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)などが主体となるケースもあります。特に大型開発や市街地再開発と連動するようなプロジェクトでは、このような形態が取られることもあります。
2. 区画整理の仕組みと流れ|土地はどう変わる?
区画整理では、地域の土地を一度まとめて整備し直し、新たな形で再配分します。
ただし、この過程では注意すべき点がいくつかあります。
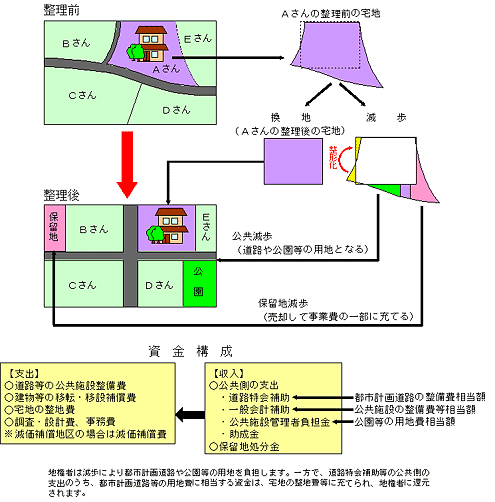
①減歩(げんぶ)で土地が減ることがある
整備の際には、新たな道路や公園などの公共スペースを確保する必要があります。そのため、土地所有者はその一部を提供しなければならず、結果としてもとの面積より少ない土地になることがあります。これを「減歩」と呼びます。
②土地の場所や形が変わるケース
換地により、もともとの土地とは異なる場所や形の土地が割り当てられるケースもあります。「前の場所に戻れる」とは限らないため、事前の確認が重要です。
③建物の移転・解体が必要な場合も
道路の拡幅や区画の変更に伴って、現在ある建物が立ち退きや解体の対象になることもあります。とくに自治体から「建物移転」の案内が届いた場合は、早めに検討しましょう。
④住所変更時の手続きも忘れずに
区画整理に伴い「住所が変更」になるケースもあります。住民票や戸籍の変更は自治体側で自動的に処理されることが多いですが、以下のような個別手続きは自分で対応する必要があります。
- 登記簿上の住所変更(不動産登記)
- 運転免許証やマイナンバーカードの住所変更
- 銀行口座やクレジットカードの登録住所変更
- 生命保険や各種契約の変更届出
- 勤務先・取引先への住所変更連絡
手続き漏れがあると郵便物が届かなくなったり、重要な通知を見逃す可能性があるため、整理して一つずつ対応しておきましょう。
3.知っておきたい!区画整理で使われる主要な用語
換地(かんち)
「換地」とは、区画整理により元の土地とは別の場所に土地を割り当て直す仕組みです。
道路の整備や土地の形を整えるため、元の土地の場所や形、面積が変更されることがあります。
基本的には「評価額が同等になるよう調整」されますが、多少の差が出た場合には「清算金」が発生します。
保留地(ほりゅうち)
保留地とは、区画整理後に売却して事業費の一部に充てるための土地です。
住民に割り当てられる「換地」とは異なり、事業者側が保有するため「保留地」と呼ばれます。
駅近や角地など利便性の高い場所に設定されることも多く、販売されるケースがあります。
区画整理に協力するため、土地所有者がもとの土地の一部を提供することを「減歩」といいます。
減歩には次の2種類があります。
- 公共減歩
道路・公園・上下水道などの公共施設整備に使われる分。
- 保留地減歩
事業の資金を得るため、施行者が売却用の土地(保留地)を確保するための分。
例:100㎡の土地を持っていた場合、10~15%程度の減歩が行われ、残りが新しい土地(換地)として戻ってきます。
清算金(せいさんきん)
清算金とは、換地によって生じた土地の価値の差額を調整するお金のことです。
- 元の土地より評価が高くなった場合:施行者に差額を支払う(納付)
- 元の土地より評価が低くなった場合:施行者から差額を受け取る(収受)
金額は専門家によって査定され、通知されます。
参照:安城市 清算金について
施行者(しこうしゃ)
施行者とは、区画整理を実施・管理する主体のことです。
多くの場合は市区町村などの自治体が該当しますが、一部は民間の組合や開発会社が担うこともあります。

4.区画整理のメリット・デメリットを徹底比較
区画整理とは、都市の再整備を目的として行われる大規模な事業です。街全体の利便性や資産価値の向上につながる一方で、土地所有者にとっては負担や制約も伴います。ここでは、土地を所有している立場から見たメリット・デメリットの両面をわかりやすく整理してご紹介します。
土地所有者にとってのメリット
① 街の安全性・利便性が向上する
- 道路幅が広がることで、車両や緊急車両の通行がしやすくなる
- 公園や排水施設が整備され、防災機能が強化される
- バリアフリー化や歩道の整備により、暮らしやすい街に変わる
② 土地の資産価値が高まる可能性
- インフラ整備や街並みの改善により、不動産の評価が上がることも
- 駅や商業施設へのアクセスが良くなれば、地価が上昇する傾向もある
③ 土地が整形地になることで活用しやすくなる
- 土地の形状が整えられ、建て替えや分筆、売却がしやすくなる
- 利用価値が高まることで、将来的な資産活用の幅が広がる
土地所有者にとってのデメリットと注意点
① 減歩(げんぶ)によって土地の面積が目減りする
- 公共施設用地の確保のために、従来の土地面積より減ることが一般的
- 特に面積が小さい土地では、使いづらくなるケースもある
② 土地の形や位置が変わる可能性がある
- 「換地」により、土地の位置や形状が変更される
- 整形地になる場合もあるが、想定外の配置になることもある
③ 建物の移転や仮住まいが必要になることがある
- 建物が解体・移転対象になった場合、引越しや建て替えが必要になる
- 仮住まい費用や引越し費用など、自己負担が発生することも
④ 計画や工事の完了まで長期間かかることがある
- 区画整理とは数年から十数年に及ぶ長期プロジェクトであることが多い
- その間は建築制限など、土地活用に一定の制約が生じる場合がある
区画整理は、地域全体の利便性や資産価値の向上に寄与する一方で、土地所有者には負担や変化も伴います。
そのため、事業内容や補償制度をよく理解した上で、冷静に対応していくことが大切です。

5.区画整理にかかる費用と補償制度:自己負担はどれくらい?
区画整理事業の費用負担の仕組み
区画整理とは、道路や公園、公共施設などを整備しながら、土地の形状や利用状況を見直す都市計画事業のことです。行政主導で行われ、個人の土地や住まいが移転の対象となることもあります。
こうした場合、原則として費用は行政が負担し、適切な補償が行われます。個人の財産に影響が及ぶため、建物の移転や土地の減少などには一定の補助や補償が設けられているのが特徴です。
とはいえ、すべての費用が公費で賄われるわけではなく、状況によっては自己負担が発生するケースもあります。
建物移転補償とは?対象となる費用
区画整理によって土地が移動または縮小された場合、建物の移転や解体が必要になることがあります。このとき、次のような費用が発生し、内容によっては自己負担になることもあります。
- 建物の移転・解体に伴う費用(補償対象外の部分)
- 仮住まいの家賃や引越費用の一部
- 移転後の再建築やリフォームの設計費・建築費
- 減歩(げんぶ)によって土地面積が減ることで発生する追加費用
これらは事業の内容や自治体によって異なります。補償の対象範囲や金額は必ず事前に自治体へ確認しましょう。
清算金(交付・徴収)の仕組みと計算方法
区画整理では、土地の形状が整えられる代わりに、面積が多少減る「減歩」が行われることがあります。このとき、土地の評価額や面積の変化に応じて「清算金」という金銭のやり取りが発生することがあります。
- 交付金:整理後の土地の価値が下がった場合に、補填として受け取る金額
- 徴収金:整理後の土地の価値が上がった場合に、追加で支払う必要がある金額
清算金の有無や金額は、土地の評価や整備内容によって個別に決まるため、具体的な金額は自治体の説明会や資料で確認が必要です。
区画整理で建物の解体が必要になった場合、解体工事は自治体などが手配するケースもありますが、状況によってはご自身で業者を選べることもあります。
「自治体から案内が来たけれど、どう動けばいいのか分からない」「信頼できる解体業者を自分で探したい」といった不安を感じている方は、ぜひ私たちにご相談ください。
6.区画整理と自宅・土地の関係:建て替え・売却・相続への影響
区画整理は、街全体の利便性や安全性を高めることが目的ですが、実際には自宅の建て替えや相続・売却などにも影響を及ぼします。ここでは、区画整理が不動産にどのような影響を与えるのかを解説します。
■ 建て替えやリフォームはできる?
区画整理の対象区域内では、「仮換地(かりかんち)」と呼ばれる期間中、一時的に建築制限がかかることがあります。制限の内容としては、以下のような例が挙げられます。
- 新たな建物の建築や増改築が一部制限される
- 建て替えには自治体の許可が必要となる
- 許可されても建物の配置や大きさに条件がつくことがある
将来的に建て替えやリフォームを検討している場合は、計画のタイミングや制限内容を早めに自治体に確認しておくことが大切です。
■ 不動産価値は下がる?上がる?
区画整理が進行中の土地は、流動性が下がり一時的に「売りにくい」「価格交渉で不利になる」といったデメリットがあります。しかし、事業が完了すると次のようなメリットも期待できます。
- インフラの整備による生活利便性の向上
- 公園や公共施設の整備による住環境の改善
- 地域全体の資産価値の見直しによる価格上昇
つまり、「一時的に不安定でも、長期的には価値が向上する可能性がある」というのが現実です。
■相続・売却時の注意点
区画整理中の土地を相続や売却する場合、以下のような点に注意が必要です。
- 換地処分(新しい土地の位置)が確定していないと、登記や売買が難しい
- 固定資産税や不動産評価額が整理中は不安定になる
- 売却しようとしても買い手が付きにくいケースがある
また、相続税や贈与税の算定において、仮換地の段階では評価額の算出が複雑になることがあります。状況によっては、特例の対象になる場合もありますので、事前に税理士や不動産の専門家に相談しておくと安心です。
■農地の区画整理:都市化への影響と対応
農地が区画整理の対象になる場合、その土地は将来的に宅地へ転用されることが多くなります。これにより、以下のような影響が出る可能性があります。
- 農地のままではなくなることで、固定資産税が大幅に上がる
- 転用の許可申請や農地法の対応が必要になる
- 相続・売却時に「農地から宅地へ変わる見込みの土地」として評価される場合がある
農地が都市計画区域に含まれている場合、早めに地目変更や活用計画を立てておくことが重要です。地元の農業委員会や市町村の都市計画課に相談することで、転用や売却のタイミングを適切に判断できます。

7.区画整理が「まだ関係ない人」にも重要な理由
「うちは対象エリアじゃないから関係ない」と思っていませんか?
区画整理は長期的な都市整備計画の一部であり、将来的に対象となる可能性もあります。
将来の区画整理に備えるには?
自治体の都市計画では、10年・20年先を見据えた整備が行われています。そのため、次のような準備が将来の安心につながります。
- 周辺地域の都市計画マスタープランを調べておく
- 市区町村の説明会・パブリックコメントに参加する
- 相続や土地活用の方針を家族で話し合っておく
空き家・実家を持つ人が注意すべきこと
親が住んでいた家や使っていない空き家が対象になると、次のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 親族で移転・解体の対応方針が決まっていない
- 管理費用や固定資産税だけが発生する
- 連絡先や手続き方法が不明で対応が遅れる
放置せず、今のうちに話し合いや登記状況の確認をしておきましょう。
近隣が区画整理された場合の影響
自分の土地が対象外でも、周囲で区画整理が始まると影響を受けることがあります。
- アクセス性や商圏の変化
- 土地価格の変動(上昇・下落)
- 開発による人口・交通の変化
つまり、「区画整理=自分ごとになる可能性がある」という視点で、情報収集や備えが重要です。
8.区画整理の進み方と期間
区画整理は数年~十数年にわたって行われる長期的な事業です。いつどんなことが起きるのか、あらかじめ知っておくことで安心して対応できます。
区画整理の基本的な流れ
一般的な流れは以下の通りです
- 都市計画決定・事業計画の策定
- 地権者への説明・意見聴取
- 換地設計と仮換地指定
- 建物移転・インフラ工事
- 換地処分(新しい土地の確定)
- 登記変更・事業完了
工事中の生活への影響
事業規模によって異なりますが、工事は5年〜15年程度かかることがあります。その間、次のような影響があります。
- 騒音や通行制限による生活上の不便
- 一時的な建築制限(新築・リフォーム)
- 仮住まいや引越しの必要が生じるケースも
区画整理の相談先
困ったとき、迷ったときは以下の窓口を活用しましょう。
- 市区町村の都市整備課・再開発担当部署
- 区画整理組合(設立されている場合)
- UR都市機構など再開発支援機関
- 土地家屋調査士、不動産会社、税理士 などの専門家
9.まとめ
区画整理とは、老朽化した街並みやインフラを再整備し、安全で利便性の高い街へと再生するための都市計画制度です。
道路の拡幅や公園の新設、土地の形状変更などが行われることで、地域全体の資産価値や住環境が向上します。
その一方で、土地の位置が変わったり、立ち退きや建物の解体が必要になったりと、所有者にとっても大きな変化が生じます。
ただし、原則として行政から立ち退き費用や仮住まいの補償が支払われるため、自己負担の心配はほとんどありません。
ご自身の土地が区画整理の対象かどうかを調べるには、市区町村のホームページを確認したり、自治体の都市計画課に相談するのが確実です。今後の計画を正しく理解し、必要な準備を進めておくことが、安心して生活を続けるための第一歩です。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄





 0120-479-033
0120-479-033