二世帯住宅の建て替え費用はいくら?タイプ別の相場と注意点を解説
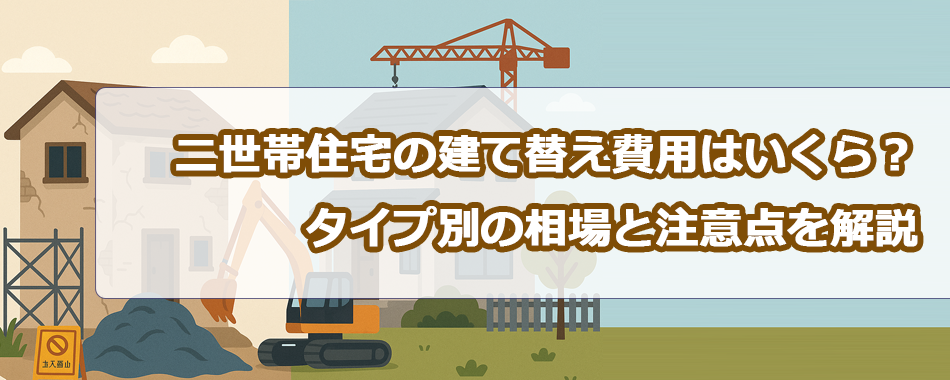
親の老後や相続をきっかけに、「実家を二世帯住宅に建て替えようか」と考える方が増えています。
とはいえ、「いくらかかるのか?」「どのタイプがいいのか?」「失敗しない方法はあるのか?」など、不安や疑問も尽きません。
特に建て替え費用は、完全分離や共有型などタイプによって大きく変わり、補助金や仮住まい費用なども含めると予想以上の出費になることもあります。
そこで本記事では、二世帯住宅のタイプ別の費用相場から、注意点、費用を抑える工夫、失敗しないための準備までを丁寧に解説します。
二世帯住宅の建て替えを考えるときの基本情報
二世帯住宅を建て替える場合、まず考えるべきは「生活の分け方」と「かかる費用の全体像」です。
同居型・共有型・完全分離型によって間取りもコストも大きく変わるため、計画を始める前にそれぞれの特徴と予算感を押さえておきましょう。
二世帯住宅とは?同居型・部分共有・完全分離の違い
二世帯住宅とは、親世帯と子世帯が同じ敷地・建物で暮らす住宅のことです。
ただし「同じ家で暮らす」といっても、生活空間の分け方によって大きく3つのタイプに分かれます。
| タイプ | 特徴 | 向いている家族構成 |
|---|---|---|
| 同居型 | 玄関・キッチン・風呂などすべて共用 | 家族間の距離が近くても問題ない場合 |
| 部分共有型 | 玄関や水回りの一部を共用し、生活空間は分離 | コストを抑えつつプライバシーも確保したい場合 |
| 完全分離型 | 玄関・水回りすべて別。二つの家が独立 | 互いに干渉せず、将来の相続や賃貸も考えたい場合 |
どのタイプが最適かは、「生活スタイル」「将来の介護」「家族間の関係性」「予算」などに応じて異なります。
まずはそれぞれの特徴を整理し、家族で共通認識を持つことがスタートラインです。
建て替えにかかる主な費用項目(本体・解体・諸経費など)
二世帯住宅への建て替えでは、建物本体の工事費だけでなく、さまざまな費用が発生します。
予算オーバーを防ぐには、必要な費用を「見える化」しておくことが重要です。
| 項目 | 内容 | 費用目安(税込) |
|---|---|---|
| 建物本体工事 | 本体の建築費用(基礎・構造・内装・設備など) | 約2,000〜4,500万円以上 |
| 解体費用 | 既存の家を取り壊す工事 | 約100〜300万円程度 |
| 仮住まい費用 | 建築中に住む賃貸や引っ越し、荷物保管など | 約50〜150万円 |
| 設計・申請費 | 設計士・建築士への報酬、確認申請・登記などの手続き費用 | 約50〜150万円 |
| 外構・付帯工事 | 駐車場・フェンス・庭・給排水の引き直しなど | 約100〜300万円 |
最初の段階で「総額でいくらまで出せるか」を明確にしておくことで、無理のないプラン設計が可能になります。
リフォームと建て替え、どちらが現実的?
「今ある家を活かすべきか、それとも新しく建て直すべきか」二世帯住宅を考えるとき、多くの人が直面する悩みです。
リフォームと建て替えにはそれぞれメリット・デメリットがあり、一概にどちらが正解とは言えません。費用面だけでなく、「家族の暮らし方」「建物の老朽化の程度」「将来のライフプラン」など、さまざまな観点から総合的に判断することが大切です。
| 項目 | リフォーム | 建て替え |
|---|---|---|
| 初期費用 | 抑えやすい(数百〜1,500万円程度) | 高額(2,000〜5,000万円前後) |
| 工期 | 短め(数週間〜数ヶ月) | 長め(数ヶ月〜1年程度) |
| 間取りの自由度 | 現状の構造制限あり | 自由設計が可能 |
| 耐震・断熱性能 | 補強工事で改善可能(限界あり) | 最新基準で対応可能 |
| 申請・手続き | 範囲によって不要な場合も | 設計・確認申請などが必須 |
特に二世帯住宅では、共有・分離の設計が必要となるため、構造の制約が多いリフォームでは十分な満足が得られない可能性もあります。
一方、建て替えは高額ですが、将来の介護や相続まで見据えた住まいづくりが可能です。
「何年住むのか」「親の介護はどうするのか」「相続の見通しは?」といった視点も交えて、総合的に判断することが後悔のない選択につながります。

二世帯住宅の建て替え費用相場|タイプ別に比較
二世帯住宅の建て替え費用は、間取りの分け方や生活空間の共有度合いによって大きく異なります。
完全同居型であれば比較的安価に済みますが、完全分離型になると設備が2世帯分必要になり、費用も倍近くに膨らむことがあります。
ここでは、代表的な3タイプ「同居型・部分共有型・完全分離型」それぞれの費用相場や内訳、注意点を詳しく解説します。
完全同居型
完全同居型の二世帯住宅とは、玄関・リビング・キッチン・浴室などをすべて親世帯と子世帯で共有するタイプです。
建築コストが抑えられるのが最大のメリットで、二世帯住宅の中では最も経済的に建て替えがしやすい形式です。
- 延床面積:約35〜40坪
- 建築費用:およそ2,000万〜3,000万円程度(地域・仕様による)
注意点
- プライバシーの確保が難しく、音や生活習慣の違いでストレスになる可能性
- 食事や入浴、来客のタイミングが重なるとトラブルになりやすい
- 将来的に世帯分離したいと思っても構造的に難しい場合がある
親子間の関係性が良好で、生活習慣に大きな差がない家庭に向いています。
コスト重視で考える場合は有力な選択肢ですが、生活上のルールを事前にしっかり決めておくことが成功のカギになります。
部分共有型
部分共有型の二世帯住宅は、玄関や浴室、キッチンなどを一部共有しながら、生活空間の大半を分けるスタイルです。
完全同居型よりプライバシーが保たれ、完全分離型より建築費用を抑えられるという“いいとこ取り”の形式として選ばれることが多くなっています。
- 延床面積:約40〜50坪
- 建築費用:およそ2,500万〜4,000万円程度(共有範囲・仕様による)
- 注意点
- 共有する部分の使用時間や清掃など、ルール決めが必要
- 生活動線が重なる場合、思わぬ干渉や摩擦が生じることも
- 完全分離ほどの資産価値や賃貸活用の柔軟性は期待しにくい
費用と暮らしやすさのバランスを重視する場合に適しており、「親世帯と程よい距離感を保ちたい」「同居はしたいが干渉しすぎたくない」という家庭に向いています。
完全分離型
完全分離型の二世帯住宅は、親世帯と子世帯の生活空間をすべて独立させる形式です。
玄関・キッチン・浴室・トイレ・リビングなど、すべて別々に設置されるため、実質的には「2つの家が1つの建物に共存している」イメージです。
| 項目 | 概要 | 費用目安(参考) |
|---|---|---|
| 建物本体 | 2世帯分の住宅(延床50〜60坪) | 約3,500〜5,000万円以上 |
| 設備費 | キッチン・浴室・トイレなど全て2セット | 約400〜800万円 |
| 設計・申請・外構費 | 登記・設計・外構・庭・駐車場など | 約200〜400万円 |
- 注意点
- 建築費用が最も高く、予算面での調整が必要
- 各所に設備が2つずつ必要なため、光熱費・修繕費も増える
- 「一緒に住んでいる実感が持てない」と感じるケースも
特に、将来的に二世帯の独立性を重視したい方や、相続対策・賃貸活用を見据えたい家庭には有力な選択肢です。
ただし、構造が複雑になる分、設計段階での調整や見積もり確認は必須です。
建築タイプ別・延床面積別で見る費用目安と選び方
二世帯住宅の建て替えでは、「建築タイプ(同居型/部分共有型/完全分離型)」によって費用が大きく異なるのはもちろんですが、延床面積によっても建築コストは大きく変動します。
ここでは、スタイル別・面積別の費用シミュレーションと、各タイプの向き不向きを表で整理し、自分たちに合った選択肢を考える材料にしましょう。
【費用シミュレーション】タイプ×延床面積別の建築費用目安(本体工事のみ)
| 建築タイプ | 40坪(約132㎡) | 50坪(約165㎡) | 60坪(約198㎡) |
|---|---|---|---|
| 完全同居型 | 約2,000〜2,800万円 | 約2,500〜3,300万円 | 約3,000〜3,800万円 |
| 部分共有型 | 約2,500〜3,500万円 | 約3,000〜4,000万円 | 約3,500〜4,800万円 |
| 完全分離型 | 約3,200〜4,200万円 | 約4,000〜5,000万円 | 約4,800〜6,000万円 |
※上記は本体工事費の概算です。設計費・解体費・仮住まい費・外構工事などは別途必要になります。
「建築タイプ」×「坪数」によって、同じ家族構成でも1,000万円以上の差が出るケースもあります。
【スタイル別比較】家族関係とライフスタイルに合った選び方
| タイプ | 費用感 | プライバシー | 家族の距離感 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 完全同居型 | 約2,000〜3,000万円 | 低い | 近い | 親子関係が良好でコスト重視の場合 |
| 部分共有型 | 約2,500〜4,000万円 | 中程度 | 適度な距離感 | 干渉しすぎず、予算も抑えたい場合 |
| 完全分離型 | 約3,500〜5,000万円以上 | 高い | 独立 | 相続・賃貸を見据えた二世帯計画 |
単に予算だけで決めるのではなく、将来的な家族の生活スタイルや介護・相続まで見据えた設計が重要です。

建て替えにかかる費用を抑えるための工夫
二世帯住宅の建て替えは、どうしても高額になりがちです。しかし、設備や間取りの工夫、補助制度の活用などによって、費用を抑えることは十分可能です。
ここでは、具体的なコストダウンの方法を紹介します。
設備や仕様のグレードで大きく変わるコスト
建て替え費用を左右する大きな要因のひとつが、住宅設備や内装・外装の仕様グレードです。
キッチン、浴室、トイレ、床材、外壁など、どこにどれだけコストをかけるかによって、総額は数百万円単位で変動します。
- キッチンや浴室のグレード(標準仕様 vs ハイグレード仕様)
- 床材・壁材・サッシの断熱性や素材
- 外壁・屋根のデザイン性や耐久性
- 太陽光発電や全館空調などの設備導入
どの部分に予算をかけ、どこを標準仕様に抑えるかは、事前に優先順位を家族で共有しておくことが大切です。
「高性能なキッチンは共用」「親世帯はシンプルでもOK」など、家族の生活スタイルをもとにコスト配分を検討しましょう。
延床面積と間取りの工夫で予算内に抑える方法
建て替え費用を抑えるうえで、延床面積と間取りの設計は極めて重要です。
家が広くなれば当然建築費も上がりますが、「無駄なスペースを削る」「共有部分を効率よく使う」といった工夫で、費用と快適さのバランスを保つことが可能です。
- トイレ・洗面所・浴室など水回りを近接配置して配管費を削減
- 家族が集まるリビングを広く、個室をコンパクトに設計
- 廊下を極力なくし、空間を効率よく使うプランに
- 階段や収納を世帯で共有することで建材や施工費を削減
特に部分共有型の場合、共用スペースの活用次第で延床面積を大きく抑えられる可能性があります。
家族の人数やライフスタイルを踏まえ、「使う空間に絞った設計」を行うことで、費用だけでなく光熱費や固定資産税の節約にもつながります。
補助金や助成制度は利用できる?
二世帯住宅の建て替えには多くの費用がかかりますが、国や自治体の補助金・助成制度を上手に活用すれば、数十万円〜100万円以上のコスト削減も可能です。
ただし、注意すべき点は、補助の対象が「二世帯住宅そのもの」ではないということです。支援制度の多くは、省エネ性・バリアフリー性・耐震性など、建物の性能向上を目的とした新築や改修に対して提供されています。
利用できる主な制度(2025年時点)
| 制度名 | 内容 | 補助金額の目安 |
|---|---|---|
| 子育てエコホーム支援事業 | 長期優良住宅やZEH住宅を対象に、環境性能に応じた補助金を交付 | 最大100万円/世帯 |
| 介護保険の住宅改修補助 | 要介護認定者に対して、手すり設置・段差解消・スロープ設置など | 最大20万円(1割負担あり) |
| 地方自治体の独自制度 | 耐震化、バリアフリー化、空き家活用などを目的にした補助制度 | 市区町村により異なる(最大30万円程度が多い) |
補助金の対象は、建物の性能や条件によって決まります。「二世帯住宅」や「建て替え」であること自体では判断されず、設計内容や認定基準の適合が求められます。
活用のポイントと注意点
- 事前申請が必要な制度が大半であり、着工後は申請できないケースもあります。
- 補助金制度の併用が制限されている場合もあるため、使いたい制度の重複可否を確認しましょう。
- 地方自治体の支援制度は年度ごとの予算で変更・終了することが多いため、必ず最新の公式情報をチェックしましょう。
建築会社や行政書士に「該当地域の制度に該当するか」を早めに確認してもらうのが安心です。
このように、補助金制度の正しい理解とタイミングを押さえておくことで、建て替え費用の大幅な軽減が可能になります。

建て替え前に考えておくべき3つの視点

二世帯住宅の建て替えを成功させるためには、費用や間取りだけでなく、将来の生活設計や家族間の関係性も重要な要素です。
ここでは、建て替え前に検討すべき3つの視点について解説します。
①将来の生活・介護・相続を見据えた間取り設計
二世帯住宅の間取りを考える際には、「今住みやすい」だけでなく、「将来も無理なく住み続けられるか」が重要な視点になります。
親の介護や世帯分離、相続後の活用など、ライフステージごとの変化に対応できる設計が理想です。
将来の生活設計や相続も見据えた間取りづくりには、次のような観点が欠かせません。
- 親世帯が将来的に介護を必要とする場合に備えて、1階に寝室・トイレ・風呂を配置
- 世帯ごとの独立性を確保しておくことで、将来の分離居住や賃貸活用にも対応可能
- 相続後に一方の世帯が退去した場合でも、使い勝手の良い間取りにしておく(可変性のある設計)
また、バリアフリー化や室内の段差解消など、高齢化を見据えた設計も早めに取り入れておくことで、後から大規模な改修をせずに済むこともあります。
②親子間・夫婦間の費用負担と名義のトラブル回避
二世帯住宅の建て替えでは、建物や土地の名義、費用の負担割合など、お金に関するトラブルが起きやすくなります。特に、親が土地を所有していて子が建物を建てるケースや、夫婦のどちらかの親との同居など、関係性によって課題は複雑になります。
家族間の信頼があっても、口約束や曖昧なままでは、相続や離婚・介護といった人生の転機で問題が表面化することがあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、次のような対策が有効です。
- 建物の名義と出資比率を明確にしておく(贈与・持分などの整理)
- 税理士や司法書士など三者を交えて「誰が・何を・どれだけ」負担するかを文書化
- 相続時に揉めないよう、遺言書や遺産分割協議の準備も検討
- 融資を利用する場合は、ローンの債務者と所有権の整合性を確認
トラブルを未然に防ぐためには、信頼よりも仕組みです。
専門家を交えた冷静な話し合いが、家族関係を壊さずに進める鍵となります。
③実際の住み心地やプライバシーへの配慮
二世帯住宅を建てるうえで、「間取り」「費用」「法的なこと」だけでなく、実際の住み心地を想像して設計に反映させることが大切です。
図面上では分かりにくい家族間の距離感や生活音の問題は、住み始めてから後悔することが多いポイントです。
特に注意したいのが以下のような点です。
- 生活リズムの違いによるストレス(就寝・起床・食事・入浴など)
- 足音・声・テレビなどの生活音が気になる位置関係
- 来客時の動線が交錯しやすい間取りや玄関共有の不便さ
- 共用スペース(廊下・階段・リビング)の使い方ルールが曖昧なままになっている
対策としては、遮音性の高い建材を使う、玄関やトイレの配置に配慮する、世帯ごとの生活動線を分けるなど、
“精神的に干渉しすぎない構造”をつくることが、長く気持ちよく暮らすための鍵となります。

二世帯住宅の建て替えでよくある後悔と失敗例
二世帯住宅は、家族みんなが安心して暮らせる理想の住まい。そう思って建て替えたものの、「こんなはずじゃなかった…」という声も少なくありません。
実際には、費用の負担が想定以上だったり、間取りや生活スタイルの違いによって、暮らしにくさを感じるケースも多くあります。
ここでは、二世帯住宅の建て替えでありがちな失敗例を具体的に紹介し、後悔しないために事前に備えておくべきポイントを考えていきましょう。
「費用が予算を超えた」「仮住まいでトラブル」などの声
二世帯住宅の建て替えで最も多い後悔のひとつが、「想定以上にお金がかかった」という点です。
その原因は、追加工事や仕様変更、仮住まいの費用の見落としなど、計画段階では気づきにくい出費が積み重なることにあります。
よくある失敗として、以下のようなケースがあります。
- 解体してみたら地盤が弱く、数百万円の地盤改良が必要に
- 外構やフェンス、駐車場工事の費用を見積りに含めていなかった
- 仮住まい期間が延び、家賃と引っ越し代が想定以上にかさんだ
- 新居に持ち込んだ家具がサイズや雰囲気に合わず、買い替えることに
建て替えでは「建物本体の工事費」だけに目が行きがちですが、解体・仮住まい・登記・外構といった諸費用も忘れてはいけません。安心して進めるためには、本体費用に加えて、少なくとも300〜500万円程度の余裕をもった資金計画を立てておくのがおすすめです。
また、仮住まいは生活環境が大きく変わるため、家族にとって大きなストレスになることも。
工事スケジュールとあわせて、早めに仮住まい候補を検討・確保しておくことが、スムーズな建て替え成功のカギになります。
「同居のストレス」「音問題」など生活上の課題
建て替え自体は成功しても、実際に暮らし始めてからストレスを感じるケースは少なくありません。
特に多いのが、「思ったより生活リズムが合わない」「音が気になる」「気を遣い続けて疲れる」といった生活上の問題です。
以下のような声がよく聞かれます。
- 親世帯と就寝時間が違い、テレビ音や足音が気になる
- 来客時の導線や駐車スペースの取り合いが発生
- 共用スペースでのルールが曖昧でモヤモヤが蓄積
- 子育てと介護の両立で家庭内の負担が偏った
対策としては、遮音・動線・世帯ごとのプライバシー確保を設計段階で重視することが重要です。
また、生活ルール(掃除・来客・ゴミ出しなど)を最初に決めておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
よくある原因と、後悔しないための対策
二世帯住宅の建て替えで失敗や後悔が起きる背景には、いくつかの共通した原因があります。
その多くは、「話し合い不足」「想定の甘さ」「第三者の視点の欠如」に起因しています。
主な原因としては以下のようなものが挙げられます。
- 家族間での希望や条件をすり合わせずに進めてしまった
- 将来の変化(介護・相続・子の独立など)を見据えていなかった
- 設計や仕様を建築会社任せにしすぎて、生活に合わない家になった
- 完全分離にすれば安心と思い込み、過剰投資になった
対策としては、次の3点が効果的です。
- 家族全員の希望・不安・将来像を事前にリストアップし、共有する
- 設計段階から建築士やFPなど第三者の意見を取り入れる
- 「今どう住むか」だけでなく「10年後どう暮らすか」を基準に判断する
十分な話し合いと情報収集を重ねることで、住み始めてからの不満やストレスを大きく減らすことができます。
計画段階こそが、後悔を防ぐ最も重要なフェーズです。
あなたにとって最適な二世帯住宅を実現するために
二世帯住宅は、親世帯と子世帯が支え合って暮らす理想の住まい方の一つです。
しかし、「生活リズムの違い」「プライバシー」「建築費用」「名義・相続の整理」など、解決すべき課題も多く、家族ごとに最適な形は異なります。
そのためには、次の3つの視点で準備を進めることが大切です。
| ステップ | 考えるべきこと |
|---|---|
| 家族で方向性を共有する | 同居・部分共有・完全分離のいずれが合っているか、生活スタイルのすり合わせ |
| プランと費用のバランスを考える | 建築コスト、仮住まい費用、相続・ローン負担を長期視点で計画 |
| 既存の建物をどう扱うかを検討する | 解体・リフォーム・一部残しなど、今の住まいの扱い方を決める |
そして、もし実家を建て替えて二世帯住宅を建てる場合には、旧家屋の解体工事が必要になります。
その際におすすめなのが、解体工事の一括見積もりサービス「クラッソーネ」です。
- 全国対応、信頼できる解体業者を複数社紹介
- 見積もり・比較が無料ででき、費用相場もわかりやすい
- 解体工事に詳しいアドバイザーが中立の立場でサポート
建て替え計画の第一歩として、安心して任せられる解体業者探しからスタートすることが、スムーズな二世帯住宅実現につながります。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄








 0120-479-033
0120-479-033