古いマンションの建て替えはどうなる?費用・条件・住民の対応を解説
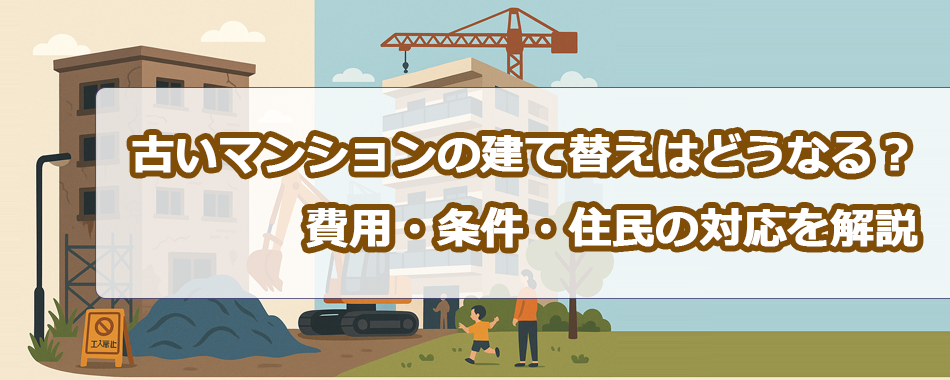
築30年、40年を超えるマンションに住んでいて、「このまま住み続けられるのだろうか?」「いずれ建て替えになるのでは?」と不安を感じている方は少なくありません。
実際に、耐震性や老朽化が進んだマンションでは、建て替えの議論が始まるケースも増えていますが、その実現には高いハードルがあります。
費用は?手続きは?住んでいる人はどうなる?
この記事では、古いマンションが建て替えになる条件や住民の費用負担、立ち退き対応などのリアルな流れを丁寧に解説します。
これから購入を考えている方にも、知っておくべき「築古マンションのリスクと判断軸」をお届けします。
古いマンションはいつ建て替えになるのか?
「築40年を超えたら建て替えになる」と思っている方も多いですが、実際には築年数だけで建て替えが決まることはほとんどありません。
実は、日本国内でマンションが建て替えに至る割合は非常に低く、多くの建物は修繕や補強で延命されています。
古いマンションが建て替え対象になる本当の条件や、実際の事例をもとに“いつ・なぜ建て替えになるのか”を解説します。
築年数だけでは建て替えにならないって本当?
「築40年」「築50年」と聞くと、“そろそろ建て替えかな”と思われがちですが、実は築年数の長さ=即建て替えではありません。
日本には築40年以上のマンションが多数ありますが、その多くは適切な修繕や改修を行いながら、今も現役で使われています。
建て替えがすぐに検討されない理由には、以下のような事情があります。
- 修繕積立金で対応可能な劣化なら、建て替えより費用負担が少ない
- 建て替えには住民の多数同意(5分の4)が必要で、現実的に合意が難しい
- 高齢世帯やローン残債がある世帯の負担が大きく、反対意見が出やすい
つまり、築年数が進んだからといってすぐに建て替えになるわけではなく、実際の劣化状況やマンション全体の運営方針、住民の意見次第で対応が大きく変わるのが現実です。
建て替えの法的条件と区分所有者の5分の4ルール
マンションの建て替えは、単なる「建物の老朽化」だけでは決まりません。
法律上、建て替えを進めるためには、区分所有法に基づく厳格な要件が定められています。
最も大きなハードルが、「区分所有者および議決権の5分の4以上の同意」です。
つまり、住民の大半が賛成しない限り、建て替えは成立しません。
■ 建て替えに必要な法的条件(2025年時点)
- 建物が老朽化し、安全性・居住性に著しい問題があると判断されること
- 区分所有者数と議決権数の各5分の4以上の賛成があること
- 管理組合による建て替え決議(総会の特別決議)
- 都道府県知事への届出と、再建計画に関する承認手続き
この「5分の4ルール」は、専有部分を複数所有している人の議決権にも影響するため、
大規模マンションや、投資用区分が多い物件では合意形成が非常に難しいのが現実です。
実際に建て替えされたマンションの事例と割合
マンションの老朽化が進んでも、実際に建て替えまで至るケースはごくわずかです。
国土交通省の「第3回マンション政策小委員会」資料によると、2023年時点で全国の分譲マンション約704万戸のうち、建て替えが実施されたのは297件にとどまっています。
これは、築50年以上のマンションが年々増加している中でも、建て替えが極めて“まれな選択肢”であることを示しています。
建て替えが実現したマンションでは、次のような条件が整っていた事例が多く見られます。
- 建物の耐震性に重大な問題があり、修繕では対応困難だった
- 区分所有者の合意がスムーズに進んだ(賛成多数の高齢者世帯が中心など)
- 建て替え後の価値上昇や再分譲による資金回収の見込みが立った
- 行政やデベロッパーの支援を受けた再開発的なスキームが組まれた
このように、「いつか建て替えられるだろう」と考えて築古マンションを購入したり住み続けるのは、やや楽観的すぎる判断かもしれません。
建て替えの現実性を知ったうえで、自分にとっての選択肢(修繕・売却・住み替えなど)を整理しておくことが大切です。

建て替えが決まったときに住民が直面すること

いざマンションの建て替えが決まると、住民は日常生活に直結する多くの課題に直面します。
自己負担額は?仮住まいはどうする?高齢世帯やローン中の人は?こうした疑問や不安が現実の問題として押し寄せてきます。
建て替えが決定した段階で発生する代表的な課題と、各世帯が準備すべき対応について具体的に解説します。
建て替え費用の自己負担はいくら?
マンションの建て替えが決定した場合、住民が最も気になるのが「結局、いくら自己負担が発生するのか」という点です。
一般的には、建て替えにかかる総費用から、積立金や補助金、再分譲益を差し引いた残りを住民が負担することになります。
ただし、その負担額は物件の規模・地域・再建方式によって大きく異なります。
目安としては以下のようなケースが考えられます。
- 修繕積立金が潤沢にあれば、自己負担が抑えられる
- 国や自治体の補助金を活用できれば、さらに軽減可能
- 新たに建てるマンションの規模やグレード次第で、追加負担が数百万円〜1,000万円超となるケースも
また、建て替え後のマンションを「再取得」するかどうかによっても費用の負担は変わります。
希望しない場合は売却・買い取りという選択もありますが、いずれにしても早い段階で費用シミュレーションを行っておくことが不可欠です。
仮住まい・立ち退き・引っ越し費用はどうなる?
マンションの建て替えが始まると、全住民が一時的に退去する必要があり、そのための仮住まいや引っ越し費用が新たな負担となります。
建て替えは通常、工事期間として1年半〜2年ほどを要するため、その間の生活費・住まいの確保が大きな課題になります。
対応は管理組合や再建方式によって異なりますが、よくあるパターンは次の通りです。
- 仮住まいは自己手配・自己負担が原則(自治体や開発事業者が一部補助する場合も)
- 引っ越し費用や荷物の一時保管料も自己負担になるケースが多い
- 中には建て替え事業者が「仮住まい先の斡旋」や「一時金支給」を行う事例もある
事前に建て替えに関する総会議事録や再建計画を確認し、「誰が・どこまで負担するのか」の取り決めを明確にしておくことが重要です。
また、長期的な生活設計の一部として、仮住まい費用をローンや補助制度でカバーできるかも確認しておくと安心です。
高齢者やローン中の世帯はどう対応すべき?
マンションの建て替えにおいて、とくに対応が難しいのが高齢者世帯や住宅ローン返済中の世帯です。
仮住まいや資金負担の問題だけでなく、住み替えや再取得への判断も複雑化しやすいのが特徴です。
特に高齢者の場合、次のような不安が現実になります。
- 長期間の仮住まい生活が身体的・精神的に負担となる
- 再取得後の住宅ローンが組めない、もしくは希望しない
- 所得の減少や年金生活により、追加費用の捻出が困難
また、現役世代でもローンを返済中の場合は、建て替え後の住戸を再取得するには二重ローンのリスクが出てきます。
こうしたケースでは、以下のような対応を検討する必要があります。
- 建て替えに参加せず、管理組合に対して「買取請求」を行う
- 地方自治体の住宅確保支援制度や高齢者向けの仮住まい補助を活用
- 家族との共有名義にして、資金調整やローン契約を工夫する
建て替えは「資産の再構築」と同時に、「生活設計の再構築」でもあります。
年齢や家族構成、今後の収入などを総合的に考慮し、無理のない方法で関わることが後悔を避けるポイントです。

建て替えの流れとスケジュールを事前に知っておこう
マンションの建て替えは、決議から解体・再建築、そして再入居に至るまで、短くても5〜8年ほどの長期プロジェクトになることが一般的です。
その間、住民には仮住まいや引っ越し、日常生活の変化といった多くの課題がのしかかります。
特に初めて建て替えに直面する方にとっては、「いつ、何が、どの順番で起こるのか?」が見えないことで不安が大きくなりがちです。
建て替え決議から再入居までの全体スケジュール
ンションの建て替えは、「建て替えよう」と決まってからすぐに工事が始まるわけではありません。区分所有者による5分の4以上の賛成を得た「建て替え決議」の後も、多くの手続きや準備が必要であり、再入居までには一般的に5〜8年ほどかかります。
以下は代表的な建て替えスケジュールの流れです。
-
ステップ1
建て替え検討・合意形成(1〜3年)
管理組合での議論、耐震診断、建築士の調査、アンケートや住民説明会などを通じて、合意形成を図ります。
-
ステップ2
建て替え決議・組合設立(半年〜1年)
区分所有法に基づき、建て替え決議を採択し、必要に応じて建て替え組合を設立します。
-
ステップ3
設計・資金計画・事業者選定(1〜2年)
設計プランを固め、資金調達や事業協力者(デベロッパー・ゼネコンなど)を選定します。
-
ステップ4
解体・建築工事(2〜3年)
現マンションの解体後、新築マンションの建設が進められます。
-
ステップ5
再取得・再入居手続き(半年程度)
完成後は登記・入居説明会・住宅ローン再設定などを経て、再入居が可能になります。
建て替えは“合意が取れればすぐ建つ”ものではなく、工程ごとに年単位の時間が必要です。長期的な視点でスケジュール管理を行いましょう。
仮住まい・子どもの転校など、生活面の変化
建て替え期間中、住民は仮住まいへの一時退去を余儀なくされます。これは法律上の義務ではありませんが、解体・建築中は安全上も生活が継続できないため、ほぼ確実に全員が一時退去することになります。
この期間(通常2〜3年)は、仮住まいの手配・家財の一時保管・生活コストの増加といった課題が発生します。
また、子どもがいる家庭では学区の変更や通学の距離問題が起こることもあり、転校を検討しなければならないケースも少なくありません。
加えて、高齢の住民がいる場合には、移動や医療機関の継続性に配慮した仮住まい選びが重要です。
建て替えは建物だけの問題ではなく、「生活全体が一時的に変わるイベント」であることを理解し、早めの情報収集と準備が不可欠です。

建て替えか修繕か?判断に迷ったときのチェックポイント
古くなったマンションに対して、「建て替えるべきか、それとも修繕で延命できるか」は、多くの管理組合や住民が直面する悩みです。
費用や合意形成の難しさだけでなく、将来の資産価値や住み心地も大きく左右される選択だけに、安易な判断は避けたいところです。
建て替えと修繕を見極めるための判断軸と、注意すべきポイントを整理して解説します。
耐震性や構造の問題はどう判断される?
マンションの建て替えを検討する際、まず重要になるのが耐震性と建物構造の安全性です。
特に1981年以前の旧耐震基準で建てられたマンションは、現行基準を満たしていない可能性が高く、地震時の倒壊リスクが懸念されます。
判断材料としては、次のような調査・評価が行われます。
- 耐震診断:専門の建築士が建物全体の構造強度を評価
- 劣化診断:鉄筋の腐食、コンクリートの中性化など、老朽化の進行度を確認
- 耐震補強の可否:修繕・補強で対応可能か、それとも建て替えが必要かを判定
なお、耐震診断は管理組合の判断で実施されるため、「建て替えの話が出る前に診断を依頼しておく」ことで、客観的な判断材料になります。
また、補強工事に多額の費用がかかる場合は、建て替えと比較して総合的に検討することが求められます。
修繕積立金と管理状況がカギになる理由
建て替えか修繕かを判断する際、建物の状態と並んで重要なのが「資金」と「管理の実態」です。
いくら修繕で対応できる建物でも、必要な費用をまかなえる積立金が不足していれば、現実的な選択肢にはなりません。
注目すべきポイントは次の通りです。
- 長期修繕計画の内容と更新状況
- 現在の積立金残高と、必要とされる修繕費の見通し
- 管理組合の運営体制(総会開催・議事録・役員体制など)
また、築古マンションでは、過去に積立金が低く設定されていたまま引き上げられていないケースが多く、
「劣化は進んでいるのに、資金が足りない」という矛盾に直面している物件も少なくありません。
修繕積立金や管理状況は、日々の積み重ねが将来の“選択肢の幅”を左右する要素です。
建て替えを視野に入れるのであれば、今のうちから管理組合の体制強化や資金計画の見直しに取り組むことが重要です。
「建て替えラッキー」は本当か?損得の境界線
マンションの建て替えが「ラッキー」と言われる理由には、いくつかの期待があります。
たとえば、資産価値の向上や物件価格が底値で買えるという点は、特に購入検討者にとって魅力的に映るかもしれません。
また、再建方式や売却スキームによっては、建て替え費用を一部免除されたり、築年数がリセットされた新築に住めるケースも存在します。
こうした期待が現実となるのは、次のような条件がそろった場合です。
- 再分譲方式や等価交換方式で、費用負担が抑えられる
- 人気エリアで建て替え後の資産価値が大きく上昇する
- 積立金が潤沢で、一時金の追加がほとんど発生しない
- 建て替えの合意形成がスムーズに進み、再取得も可能である
しかし一方で、こうした“成功例”は例外的であり、多くの築古マンションでは実現が難しい現実があります。
- 合意形成に何年もかかり、計画が頓挫するケース
- 積立金不足で数百万円の自己負担を求められることもある
- 仮住まいの確保や生活環境の変化に対応できず、ストレスが増す
- 買取請求を選んでも、市場価格より安い金額での買い取りにとどまることがある
つまり、「建て替えで得するか損するか」は物件の状況や合意状況、地域特性、資金の蓄えなど、さまざまな要因が複雑に絡み合って決まるものです。
ラッキーとされる事例を知っておくことは大切ですが、それを鵜呑みにせず、自分の物件・世帯にとって本当に成り立つのかを冷静に見極めることが欠かせません。

建て替え話が出たときにやっておくべき対応
建て替えの話が持ち上がったとき、多くの住民は戸惑いや不安を感じます。
しかし、初期の段階で何を確認し、誰に相談し、どう動くかによって、その後の負担やトラブルを大きく軽減することができます。
建て替え検討が始まった段階で住民がやるべき具体的な対応と、後悔しないための準備ポイントを解説します。
まず確認すべきは総会議事録と長期修繕計画
建て替えの話が出たとき、最初に確認すべきなのが管理組合の総会議事録と長期修繕計画です。
これらには、マンション全体の方針や財政状況、将来計画に関する具体的な情報が記録されており、「建て替えの本気度」や「修繕との比較検討」が進んでいるかを知る手がかりになります。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 最近の総会で「建て替え」や「耐震問題」が議題に上がっているか
- 長期修繕計画の見直し頻度や、次回の大規模修繕の予定
- 積立金残高と、将来的な修繕・建て替えに対する資金の見通し
- 管理会社や理事会から建て替えに関する専門家への相談履歴
特に建て替えか修繕かの判断は、管理組合内部で慎重に議論されるテーマであり、議事録はその過程を知る唯一の公的資料です。
早い段階で過去数年分を確認し、現状の動きを正しく把握することが、最も確実なリスク回避の第一歩になります。
建て替え検討の段階で相談すべき専門家とは?
建て替えの話が出始めた段階で、「誰に相談するか」は今後の方向性を大きく左右します。
管理組合内での議論にとどまらず、早い段階で専門家の客観的な意見を取り入れることが、正確な判断とトラブル防止につながります。
相談すべき専門家には、以下のような役割があります。
- 一級建築士・構造設計事務所:耐震診断や補強・建て替えの技術的な検討
- マンション管理士・コンサルタント:修繕・建て替えの費用比較や合意形成支援
- 弁護士・司法書士:区分所有者間の法的トラブル、契約内容の確認
- 不動産鑑定士・仲介会社:建て替え後の資産価値や再取得・売却のアドバイス
また、自治体や国の制度で無料相談窓口が用意されている場合もあります。
建て替えに向けた検討初期ほど、中立的な視点を持つ外部専門家を交えることで、無理のない選択肢を見つけやすくなります。
合意形成に向けた注意点とトラブル事例
マンションの建て替えで最も難航しやすいのが、住民の合意形成です。
法律上、建て替えには「区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成」が必要とされており、わずかな反対意見が全体計画のブレーキになることもあります。
合意形成でつまずく典型的な要因には、次のようなものがあります。
- 高齢者やローン返済中の世帯が再取得に消極的
- 所有者の一部が投資目的で不在、連絡が取れない
- 修繕派と建て替え派で主張が対立し、議論が平行線
- 議事運営や説明が不十分で、「不信感」だけが先行
実際に、議事録での説明不足が原因で管理組合が訴訟トラブルに発展したり、建て替えが10年以上進まなかったという事例もあります。
対策としては、次のような準備が有効です。
- 合意形成の前に説明会や個別相談会を複数回実施
- 反対意見の背景を丁寧にヒアリングし、解決策を提示
- 専門家を同席させて、客観的で中立的な進行を行う
「全員が100%納得する」のは難しくとも、信頼と情報開示を重ねることで“納得できる反対”を減らすことが重要です。

建て替えに使える補助金・制度・税制優遇
マンションの建て替えには多額の費用がかかりますが、一部の制度を利用すれば負担を軽減できる可能性があります。
たとえば、住宅金融支援機構の融資制度や、耐震・再開発に関する補助金、税金の軽減措置などが該当します。
ただし、これらの制度は対象条件や申請のタイミングが限られており、使いこなすには事前の準備が欠かせません。
住宅金融支援機構などの制度と要件
マンションの建て替えには、公的な融資や補助制度を活用できる可能性があります。
なかでも代表的なのが、住宅金融支援機構の「マンション建替融資制度」です。
これは、建替組合や区分所有者が利用できる低金利の長期融資制度で、仮住まい費用や再取得費用の一部をまかなうことが可能です。
また、地域によっては老朽マンションの再生や除却を支援する独自制度が設けられています。
たとえば東京都や大阪市では、「老朽建築物除却助成」「共同住宅再生促進事業」などが実施されています。
| 制度名 | 支援内容 | 対象者 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| マンション建替融資制度(住宅金融支援機構) | 建設資金・仮住まい資金などを低金利で融資 | 建替組合・個人区分所有者 | 組合設立と計画承認が前提条件 |
| 地方自治体の再生支援制度(例:東京・大阪) | 老朽除却・再開発に対する補助金 | 管理組合・建替組合 | 自治体によって条件・上限が異なる |
補助金や融資制度は、申請時期・要件・地域によって大きく異なるため、早い段階から建築士や行政書士に相談するのが安心です。
建て替え時の税金控除や支援制度
建て替えには多くの税金が伴いますが、一定の条件を満たせば、軽減措置や控除制度を受けられることがあります。
以下のような主要な税制優遇制度があります。
- 固定資産税の軽減措置
新築後、一定期間(例:3年間)固定資産税が半額または軽減されることがあります。 - 登録免許税の軽減
新築建物の保存登記、土地の所有権移転登記などに対する税率が引き下げられる制度があります。 - 譲渡所得の特例
旧住戸を売却する場合、「3,000万円の特別控除」や「10年超所有の軽減税率」が適用される場合があります。 - 相続税評価の圧縮効果
建て替え後の住戸を相続した場合、評価額が抑えられ、結果として相続税が軽減されることもあります。
これらの制度は個別に条件が異なり、重複適用ができない場合もあるため、税理士や専門家と連携して計画的に進めましょう。

築古マンションをこれから購入する場合の注意点
築年数が経過した中古マンションは、価格の安さや立地条件から魅力的に映ることもあります。
しかし、購入後に「建て替え話が浮上して費用負担が発生」「修繕計画が進んでおらず住みにくい」といったトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
築古マンションを購入する際に見落としがちな法的・資金的リスクと、その確認方法を具体的に解説します。
「建て替え狙い」の投資が失敗する理由
「築古マンションを安く購入し、いずれ建て替えになれば新築同様の住戸が手に入る」という“建て替え狙い”の投資は、一見お得に思えるかもしれません。
しかし、現実には計画が思うように進まず、想定以上の時間と費用を要することで、期待通りのリターンが得られないケースが多くあります。
よくある失敗のパターンは以下の通りです。
- 建て替えの合意形成が進まず、何年経っても着工できない
- 積立金が不足しており、一時金として数百万円の請求が発生
- 仮住まい期間や再取得を断念し、買い取り価格が期待以下だった
- 投資目的で複数所有していたが、住民の反感を買い建て替え反対の要因にされた
また、建て替えが実現したとしても、再取得に費用がかかる場合や、希望する住戸に住めないケースもあります。
「ラッキー」な成功例だけを鵜呑みにせず、慎重に物件と管理状況を見極めることが大切です。
購入前に確認したい法的・資金的リスク
築古マンションの購入を検討する際には、価格や間取りだけで判断してはいけません。
将来的な修繕・建て替えに関する“法的・資金的リスク”を見落とすと、思わぬ負担やトラブルに直面する可能性があります。
購入前に必ず確認すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 管理規約・総会議事録に建て替えや修繕に関する議論があるか
- 修繕積立金の残高と長期修繕計画に無理がないか
- 区分所有者の構成比(高齢化・投資目的所有など)
- 敷地・建物の権利関係が複雑化していないか(底地権・借地など)
- 将来的に再取得が必要な場合、住宅ローンや自己資金で対応できるか
特に築40年以上の物件では、「数年以内に大規模修繕や建て替えの話が出るかもしれない」前提で資金計画を立てることが重要です。
購入前には不動産会社任せにせず、自身でも必要書類を確認し、リスクと向き合ったうえで購入判断を行うようにしましょう。
再建築不可や容積率オーバーの見落としに注意
築古マンションの中には、現在の建築基準法では再建築ができない「再建築不可」や、容積率オーバーの状態で建てられている物件も存在します。
こうした“既存不適格建築物”に該当する場合、将来的に建て替えや大規模な改修ができなくなるリスクがあるため、事前確認は必須です。
具体的に注意すべきリスクは以下の通りです。
- 接道義務を満たしていない敷地にある場合、建て替え許可が下りない
- 現在の用途地域や容積率に合わない構造で建てられており、同規模での再建築が不可能
- 建て替え時に住戸数が減るため、再取得できない住民が出る可能性
- 法律上は建て替え可能でも、行政指導や制限により許可が下りにくい事例もある
とくに再建築不可物件を「将来価値が上がるかも」と期待して購入すると、売却も困難で出口がなくなるリスクがあります。
物件概要だけでなく、役所や不動産の専門家に法的制限を照会し、不明点は必ずクリアにしてから購入判断をするようにしましょう。

建て替えは『他人事』ではなく備えるべき「備えるべきこと」
マンションの建て替えは、突然自分の暮らしに降りかかる可能性がある“住まいの転機”です。
築年数や耐震性に問題がある物件であればなおさら、いつかそのタイミングは訪れるかもしれません。
「まだ先の話」と受け流すのではなく、将来に向けてどんな備えをしておくべきか、資産価値と生活の安心を守るための具体的な行動について解説します。
資産価値と生活の安心を守るためにできること
マンションの建て替えに直面したとき、慌てずに対応するためには、事前の備えと情報整理が不可欠です。
特に築古マンションでは、「資産としての価値を守れるか」「暮らしの安心を維持できるか」が、将来の大きな分かれ道になります。
以下に、住民が事前にやっておくべき対応と、それによって得られる効果をまとめました。
| 取り組むべきこと | 実施の目的・期待できる効果 |
|---|---|
| 総会議事録・修繕計画の定期チェック | 建て替えや修繕の兆候を早期に把握する |
| 修繕積立金の残高と見直し状況を確認 | 費用負担のシミュレーションに役立て、準備を始められる |
| 耐震診断や劣化診断を管理組合に働きかける | 技術的に建て替えが必要かどうかを明確にする |
| 自治体の補助制度・支援制度を調べておく | 仮住まいや建て替え費用を軽減できる可能性がある |
| 家族や相続人と方針のすり合わせをしておく | 将来的な資産処分・住み替え判断を円滑に進められる |
日頃からこうした情報を確認し、家族や管理組合と共有しておくことで、「知らなかった」「話についていけない」といった状況を防ぐことができます。
住まいを“資産”として守る意識を持ち、将来の建て替えや修繕に向けて冷静に備える姿勢が、安心した暮らしにつながります。
建て替えの現実と向き合い、正しく備えよう
マンションの建て替えは、多くの住民にとって避けて通れない“暮らしの分岐点”です。
老朽化や耐震性の不安が現実となったとき、「いつか誰かがなんとかしてくれる」と先送りにするのではなく、今、自分にできる備えを考えることが必要です。
とはいえ、建て替えの実現には法的な要件、合意形成、資金面の課題など、いくつものハードルが存在します。
「現実を直視する」とは、こうした複雑な背景と向き合いながら、自分たちの選択肢を整理することにほかなりません。
次のような意識と行動が、“後悔しない備え”につながります。
- 合意形成に時間がかかることを前提に、家族や周囲と日頃から方針を共有する
- 管理組合の議論や修繕計画に関心を持ち、自分の意見を伝える場をつくる
- 建物を「住まい」であると同時に「資産」としても捉え、長期的な視点で判断する
- 自分たちのライフステージや将来の住まい方を見据えて、柔軟に選択肢を検討する
そこでおすすめしたいのが、複数の建築・解体会社を比較しながら最適な選択肢を探せる『クラッソーネ』の無料サービスです。
- 解体や建て替えの経験が豊富な会社を一括で紹介
- 条件に合う複数社の提案・費用見積もりを比較できる
- 中立の立場のアドバイザーが、住民一人ひとりに合った方針を一緒に考えてくれる
「どこに相談すべきか分からない」「費用感や選択肢をまず知りたい」という方にとって、
専門家からのサポートを受けることは、“正しい備え”の第一歩になります。
不安の多い時代だからこそ、冷静に現実と向き合い、判断と行動に移すための情報と環境を整えていきましょう。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄








 0120-479-033
0120-479-033