築60年の家は建て替えかリフォームか?後悔しない判断の基準とは
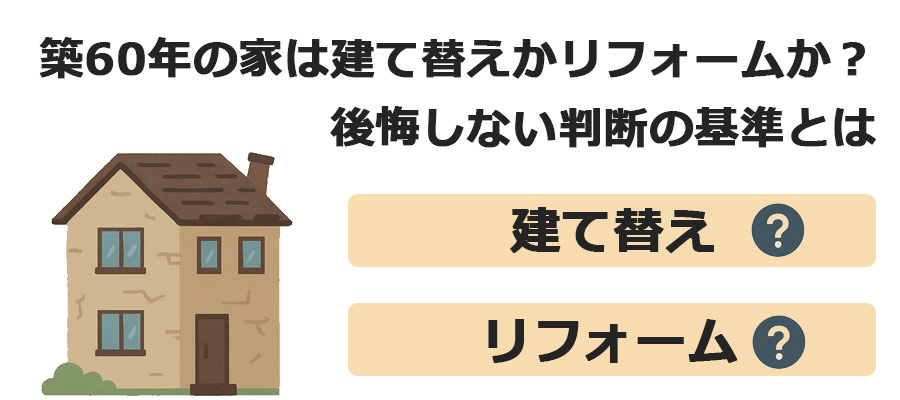
築60年という年月を経た住宅に住み続けている方の中には、「そろそろ何か手を加えるべきか…」と感じ始めている方も多いのではないでしょうか。
見た目はまだしっかりしているようでも、内部では構造や配管、耐震性能に深刻な劣化が進んでいる可能性があります。
「リフォームで住み続けるか、それとも建て替えるべきか」その判断は簡単ではありません。
この記事では、築60年の住宅に多い劣化やリスク、費用や判断の目安をわかりやすく解説し、後悔しない住まい選びをサポートします。
築60年の住宅、リフォームか建て替えか迷ったら
築60年を迎えた住宅は、見た目以上に深刻な劣化が進んでいる可能性があります。
この章では、木造住宅に多く見られる経年劣化の特徴や、安全性の落とし穴、そして実際にリフォームを選んだ方がどのような修繕を行っているのかを解説します。
築60年の木造住宅に多い劣化とリスクとは
築60年の木造住宅は、外から見ただけでは判断できない劣化やリスクが数多く潜んでいます。
長年の使用により、構造躯体・配管・断熱材・基礎部分などが目に見えないところで老朽化している可能性があります。
特に築年数の経過によって起こりやすい主な劣化は以下のとおりです。
| 劣化箇所 | 主なリスク・症状 |
|---|---|
| 柱・梁・基礎 | 木材の腐朽、白蟻被害、耐震性の低下 |
| 屋根・外壁 | 雨漏り、ひび割れ、断熱性能の著しい劣化 |
| 配管・給排水設備 | 錆や詰まりによる水漏れ、衛生面の不安 |
| 電気配線 | 被覆劣化による漏電・火災リスク |
| 断熱材 | 経年劣化による断熱性能の低下、結露やカビの原因にも |
さらに、建築当時の基準が現代の安全基準に合っていないため、大きな地震や災害時には倒壊や損壊のリスクが高まります。
築60年ともなれば、建物全体の耐久性が限界に近づいていると考えるのが現実的です。
リフォームで対応できる範囲なのか、それとも建て替えが妥当なのか、劣化状況を把握したうえで慎重に判断する必要があります。
「住めている」=安心ではない?安全性の盲点
築60年の住宅に住み続けている方の中には、「これまで大きなトラブルもなく住めているから大丈夫」と感じている方も多いかもしれません。
しかし、“住めている”ことと“安全に住める”ことは、必ずしもイコールではありません。
特に築60年前後の住宅では、以下のような安全性に関わる盲点が潜んでいます。
- 旧耐震基準のまま建てられている可能性が高く、大規模地震に耐えられない構造
- シロアリや湿気などで構造体が弱っているケースが見えづらい
- 電気・ガス設備が老朽化し、火災や漏電のリスクが高まっている
- 断熱性や気密性が低く、健康への影響やヒートショックの懸念もある
また、目に見える部分をいくら修繕しても、建物の土台や骨組みが脆ければ根本的な安全性は確保できません。
築年数が進んでいる家こそ、「何かあってからでは遅い」という視点で、建物全体の性能や強度を一度見直すことが重要です。
安全性を数値で確認できる「耐震診断」や「建物インスペクション(住宅診断)」を活用することで、見えないリスクを可視化できます。
実際にリフォームした人はどこまで直している?
築60年の住宅をリフォームする場合、多くのケースでは見た目だけでなく「構造」「設備」「性能」まで手を入れる大規模改修が必要になります。
実際にリフォームを行った人たちの多くが、以下のような箇所を重点的に修繕しています。
| リフォーム内容 | 理由・目的 |
|---|---|
| 耐震補強(柱・壁・基礎) | 旧耐震基準の建物を現行基準に近づけるため、安全性確保のために必須 |
| 配管・配線の交換 | 老朽化による水漏れ・漏電などのリスクを回避するため |
| 屋根・外壁の張替え・補修 | 雨漏り対策、美観の回復、断熱性能の向上を目的とすることが多い |
| 断熱材の交換・追加 | 夏冬の快適性と冷暖房費の節約、結露・カビの予防 |
| 水回り設備の刷新 | 使い勝手の改善と老朽設備のリスク回避のため |
これらを行うとなると、いわゆる「スケルトンリフォーム」(構造だけを残して全面改修)に近い内容となるケースが多く、
費用も1,000万〜1,500万円以上に達することが珍しくありません。つまり、築60年の住宅をリフォームするには、「どこまで直せば安全・快適に住み続けられるか」という視点を明確に持つことが重要です。
部分補修で済ませるのか、それともフルリフォームが必要なのかを、建物診断をもとに判断するのが理想的です。
築60年リフォームと建て替えの判断基準
築60年の住宅は、見た目や思い出だけで判断するにはリスクが大きすぎるタイミングです。
「もったいない」と感じる気持ちにどう向き合うか、あと何年住む予定なのか、そして必須となる建物診断と耐震基準の確認について、現実的な判断基準を解説します。
「もったいない」と感じる前に確認すべきこと
築60年の住宅には、多くの思い出が詰まっており、「壊すのはもったいない」と感じるのは自然なことです。
しかし、その感情だけで判断してしまうと、安全性や快適性を犠牲にするリスクがあります。
まず確認しておきたいのは、以下のようなポイントです。
- 建物の構造体(柱・梁・基礎)は健全か
- 屋根・外壁の劣化や雨漏りが進行していないか
- 配管・配線が現代の生活に対応できる状態か
- 断熱性や気密性が著しく低下していないか
- 耐震基準(旧耐震or新耐震)に適合しているか
こうした項目を、感覚ではなく建物診断による客観的なデータで把握することが重要です。
「まだ住める」と「安全に住める」は別の問題であり、劣化や危険性を把握せずに表面的な補修で済ませるのは、結果的に無駄な出費になる可能性もあります。
“もったいない”という気持ちを大切にしながらも、家の本当の状態を確認したうえで納得のいく判断をすることが、後悔を防ぐ近道です。
あと何年住む?が大きな判断の分かれ目
築60年の家に住み続けるか決める際、重要なのは「あと何年住むか」という視点です。
- 5〜10年程度住む予定なら
最低限のリフォームで対応。外壁や水回りなどの老朽化が気になる部分を整え、過度な費用は避けるのが経済的です。 - 20年以上住むつもりなら
建て替えで、安全性・快適性を根本的に改善する方が将来の安心につながります。
繰り返しリフォームに費用をかけると、最終的に建て替えと同じくらいのコストがかかることもあります。
そのため「あとどれくらい住むのか」を明確にしておくことが、無駄のない判断につながります。
建物診断+耐震基準のチェックは必須
築60年の住宅をリフォームするか建て替えるかを考えるなら、まずは「建物診断」と「耐震基準の確認」をセットで行いましょう。
- 建物診断(インスペクション)
構造・基礎・設備などを専門家がチェックし、劣化や修繕の必要性を明らかにします。
白蟻被害や雨漏り跡、傾きなども見つけることができます。 - 耐震診断
1981年以前の住宅は「旧耐震基準」の可能性が高く、現行基準を満たしていないことも。
数値で耐震性を把握し、補強の必要性を確認できます。
診断の結果次第で、軽微な補修で済む場合もあれば、高額な補強が必要で建て替えが妥当になることも。
見た目や勘に頼らず、現実的な判断の出発点として、診断は不可欠です。
費用が不安な方は、自治体の補助制度が使えるかも。事前にチェックしておきましょう。
築60年のリフォーム・建て替え費用の目安
築60年の住宅では、リフォームにかかる費用も建て替えの費用も、一般的な住宅より高くなる傾向があります。
建て替え費用の内訳や仮住まい費用の考慮点、そして初期費用に加えて将来必要になるメンテナンス費まで含めた、現実的な費用比較を行います。
建て替えに必要な費用と、解体・仮住まい費も考慮
築60年の住宅を建て替える場合、必要な費用は本体工事費だけではなく、解体費・仮住まい費用・登記手続き・外構工事なども含めて考える必要があります。
国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、注文住宅の建築費(本体のみ)の全国平均は約3,454万円。
ここに加えて、以下のような付帯費用がかかります。
| 費用項目 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 解体工事費 | 約100〜200万円 | 木造か鉄骨か、立地条件によって差が出る |
| 建築本体工事費 | 約1,800〜3,500万円 | 建物の規模・仕様・ハウスメーカーにより変動 |
| 外構工事費 | 約100〜300万円 | 駐車場、庭、フェンスなど |
| 登記・諸経費 | 約100〜200万円 | 建築確認申請、登記、住宅ローン事務手続きなど |
| 仮住まい・引越し費 | 約50〜100万円 | 家賃+引越し費用(2回分) |
合計:約2,200万円〜4,000万円前後
これらを見越して予算を組むことが、建て替えをスムーズに進めるための第一歩です。
また、自治体によっては解体や建築に関する補助金制度が利用できるケースもあるため、事前の情報収集も忘れずに行いましょう。
初期費用だけでなく将来的なメンテナンスも比較
住宅にかかるお金は、建てる・直すときだけではありません。
住み続ける間に必要となるメンテナンスコストも、長期的に見れば大きな負担になる可能性があります。
たとえば、築60年の家をリフォームして延命した場合、表面的には費用を抑えられても、以下のような追加費用が生じることがあります。
- 劣化した配管・電気設備の不具合修理
- 経年で再発する屋根・外壁の補修
- 結露・断熱性能不足による光熱費の増加
- 耐震補強不足による改修の再検討
建て替えを選べば、構造体・設備・断熱性が新しくなり、しばらく大きな修繕は不要です。
また、最新の省エネ基準を満たすことで、光熱費を抑えやすく、長期的な維持費の節約にもつながります。
以下は、20年間の維持費目安の一例です。
| 項目 | リフォーム住宅 | 建て替え住宅 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 約500万〜1,000万円 | 約2,200万〜4,000万円 |
| 20年間の修繕費 | 約300万〜500万円 | 約100万〜200万円 |
| 光熱費(断熱性能差) | 高くなりがち | 省エネ基準で抑えやすい |
「安く直せるからリフォーム」ではなく、「20年後にどちらが得か?」という視点で比較することが、後悔しない判断につながります。
築60年でもリフォームできる?メリット・デメリット比較
築60年の住宅は「もう直せないのでは?」と思われがちですが、建物の状態によってはリフォームで対応できるケースもあります。
この章では、リフォームと建て替えそれぞれのメリット・リスクを具体的に比較しながら、自宅に合った現実的な選択肢を見極める方法をご紹介します。
リフォームのメリット・リスク(耐震・配管・構造)
築60年の住宅でも、構造がしっかりしていればリフォームで延命することは可能です。
特に、基礎や柱が健全で、劣化が局所的である場合には、部分的な改修で住み続ける選択も現実的です。
メリット
- 初期費用を抑えやすい(建て替えに比べて1/2〜1/3程度で済むことも)
- 仮住まい不要、住みながら工事できるケースもある
- 思い出のある建物や間取りを活かせる
- 補助金やリフォーム減税制度が利用できる可能性がある
リスク
- 耐震補強の限界:旧耐震基準の建物は、補強しても新築並みの耐震性に届かないことが多い
- 隠れた劣化への対応が不十分になりやすい(配管・断熱材・床下など)
- 一度にすべて直せない場合、今後も修繕費が発生するリスクが残る
- 間取りの制限があり、生活動線や使い勝手が改善しきれないことも
築60年ともなると、リフォームでは性能回復に限界があるケースも多いため、”どこまで直せるか”を見極める目が重要です。
リフォームを前提とするなら、まずは建物診断で劣化状況を把握し、優先順位をつけた工事計画を立てることが成功の鍵です。
建て替えのメリット・注意点(資産価値・費用負担)
築60年の住宅を建て替える最大の魅力は、住宅の性能をゼロから現代基準に作り直せる点にあります。
老朽化した構造や配管、断熱材などをすべて新しくできるため、安心・快適な暮らしを長期的に実現できるのが建て替えの強みです。
メリット
- 最新の耐震・断熱・省エネ基準を満たす家にできる
- 設備もすべて新しく、将来の修繕コストが抑えられる
- 間取り・導線を一から自由に設計できる
- 資産価値を大きく回復・維持できるため、相続や売却にも有利
- 長期優良住宅やZEH仕様なら、補助金や減税も活用できる可能性あり
注意点
- 初期費用が大きく、資金計画が必須(2,000万〜4,000万円規模)
- 解体・建築中は仮住まいと引越しの手配・費用が必要
- 接道義務や用途地域など、法的な条件で建て替え不可となる可能性も
- 住宅ローンを活用する場合は、年齢や収入条件の確認も必要
築60年の住宅は、性能・安全性・維持費の面で限界を迎えている可能性が高いため、建て替えは費用以上に“安心”と“資産”という価値を手に入れる選択肢ともいえます。
ただし、建て替えを検討する際は、建築条件や資金の見通しも含めて、専門家に早めに相談するのがおすすめです。
後悔しないための3つの判断視点
築60年の家を前に、リフォームか建て替えかで迷うのは当然のことです。
ここでは、後悔しないために欠かせない3つの判断視点の「建物の状態と改善可能性」「費用対効果と資産価値」「ライフプランとの適合性」について、それぞれの具体的な考え方をご紹介します。
家の状態と性能にどれだけ手を加えられるか
築60年の住宅は、構造・断熱・配管・耐震など多方面にわたって劣化している可能性が高く、「どこまで補修・改善できるか」が、リフォームか建て替えかの判断の分かれ目です。
リフォームで対応できるかどうかは、以下の点が大きなポイントになります。
- 構造体(柱・梁・基礎)に大きな劣化やシロアリ被害がないか
- 耐震補強を行って、新耐震基準相当の強度が確保できるか
- 給排水管や電気配線の更新が現実的に可能か
- 断熱・気密性能を高める工事が施工できるか
もし、こうした項目のいくつかが「補修では限界」と判断される場合は、費用をかけても性能が十分に回復しない可能性があるため、建て替えの方が合理的です。逆に、構造体が健全で改修工事によって住環境の改善が見込める場合は、リフォームでも十分な価値を得られる可能性があります。
「どれだけ手を加えれば、どの程度改善されるか」を明確に把握することが、最初に行うべき冷静な判断軸になります。
費用対効果と資産価値の視点で見る
築60年の住宅にリフォームや建て替えを行う際は、その費用に見合う価値が得られるかを冷静に見極めることが重要です。
例えば、500万円のリフォームで部分的に快適性が向上しても、構造体の劣化や耐震性に不安が残る場合、費用対効果は低くなります。一方、建て替えには高額な費用がかかりますが、住宅の資産価値が大きく回復し、将来的な売却や相続に有利になるというメリットがあります。
また、住宅ローン減税や補助金制度を活用すれば、建て替えの実質負担を抑えられることもあります。
費用対効果を考える際は、以下の視点が有効です。
- 改修や建築によって、どれだけ生活満足度が上がるか
- 将来的にどれだけ修繕費・光熱費を削減できるか
- 資産価値の維持や、相続・売却時の影響はどうか
短期的な出費だけでなく、10年〜20年先を見据えた総コストとリターンのバランスを比較することが、後悔しない判断につながります。
将来のライフプランに合っているかどうか
リフォームか建て替えかを迷ったとき、将来のライフプランと今の家が合っているかどうかは非常に重要な判断材料になります。
- 子どもとの同居や二世帯化を考えている
- 夫婦だけの生活になり、バリアフリー化したい
- 自宅で仕事をする時間が増え、間取りを見直したい
- 老後を見据え、維持費を抑えて安心して暮らしたい
このような生活スタイルの変化に対し、現状の家でどれだけ対応できるかを見直してみましょう。
リフォームでは、限られた構造の中でできることに制約があり、「間取りが根本的に合わない」「断熱や防音性が限界」などの問題が残ることも。
一方、建て替えであれば、自由な設計で生活動線を一新できるため、今後の暮らしにフィットする住まいが実現しやすくなります。
つまり、「今ある家に自分たちの生活を合わせる」のか、「これからの暮らしに合わせて住まいを整える」のかを明確にすることが、納得できる選択につながります。
あなたにとって最適な選択をするために
築60年の住宅は、住まいとしての寿命がひとつの節目を迎える時期です。
構造や設備の老朽化だけでなく、ライフスタイルの変化や将来の住まい方を見直すきっかけにもなります。
リフォームか建て替えか、どちらが正解かは一律ではなく、家の状態と家族の将来を照らし合わせたときに「納得できるかどうか」が大切な判断基準です。
そのためには、費用だけでなく、安全性・快適性・資産価値といった多角的な視点で比較検討することが欠かせません。
特に建て替えを検討している方にとって、最初のハードルとなるのが「解体工事の費用」です。
業者によって価格差が大きく出やすいため、複数社から相見積りを取ることがコスト削減の第一歩になります。
そんなときに便利なのが、解体工事一括見積りサービス「クラッソーネ」です。
対応エリアの優良業者から一度に見積りを取り寄せることができ、比較・検討もスムーズ。
費用感の把握だけでも活用できるため、「まずは情報収集から始めたい」という方にも安心です。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄





 0120-479-033
0120-479-033